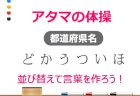ちょっとこの頃、やる気が出ない。モチベーションが続かない……。
年末年始の長すぎた“奇跡の9連休”のおかげで、かえって調子が狂ってしまった、という人もきっと多いのではないでしょうか?
そこで今回は、そんな後ろ向きな気持ちをたちまち軽くしてくれる偉人たちの名言をピックアップ。時代を動かした傑物たちのバイタリティー溢れるパワフルな言葉に触れて、サクッとエネルギーチャージといきましょう。ちなみに、インターネットの世界は玉石混交。検索すれば数多ヒットする「名言集」の中には「ホントに言ったの?」と思うような出所不明の言葉もありますよね。
でも、そこはご安心を。この特集では、名言に関する著書も多数ある偉人研究家・名言収集家の真山知幸氏に、人選および言葉のセレクトを依頼。出典の確かな「お墨付き」のある言葉だけを集めて、“最強打線”を組みました。
文/鈴木長月
坂本龍馬「なんの浮世は三文五厘よ。ぶんと屁のなるほどやってみよ」
トップバッターを任せるなら、やはりこの人。日本に“夜明け”をもたらした幕末の英雄、みんな大好き、坂本龍馬(1836~1867)しかいないでしょう。
出典は、かの有名な「日本を今一度、洗濯いたし申し候」と同じく、姉・乙女に宛てた手紙。「文久三年六月二十九日坂本乙女あて書簡」からの一節です。
三文五厘とは、現代の貨幣価値にしても100円未満という、言わば“はした金”。つまり龍馬は、「どうせこの世にはたいした値打ちがないんだから、何事もブンと屁をするくらいのつもりでやればよい」とまぁ、こう言っているわけですね。
薩長同盟も、その後の大政奉還も、龍馬ひとりが「屁をするくらいのつもりで」動いた結果として起きた出来事だと思うと、なんだか勇気も湧いてきます。

勝海舟「行蔵(こうぞう)は我に存す。毀誉(きよ)は他人の主張、我に関せず」
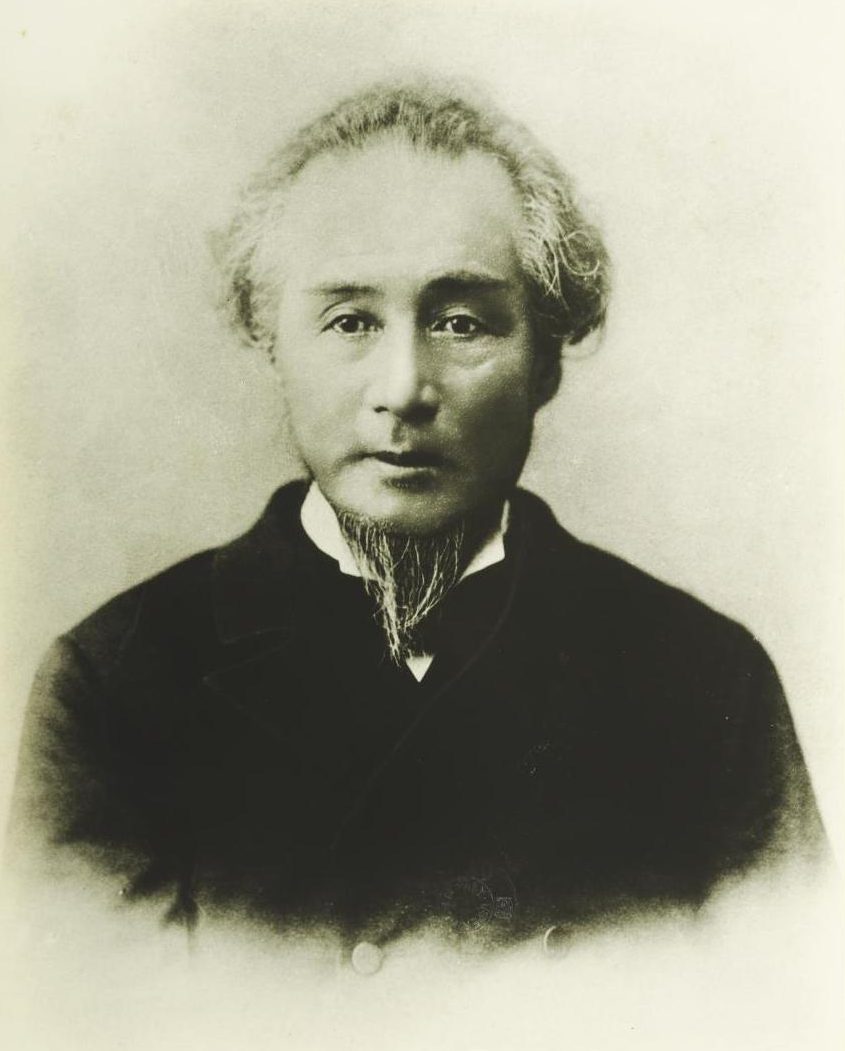
続く2番には、そんな龍馬も自ら弟子入りを志願した大人物。幕府側の交渉役として“江戸無血開城”も成し遂げた勝海舟(1823~1899)にご登場いただきましょう。
これは、著書『瘠我慢の説(やせがまんのせつ)』のなかで、彼を名指しで批判していた福沢諭吉に対するアンサーとして、勝が自ら書き送った言葉。そのときの顛末は、彼の自著『氷川清話』(講談社学術文庫ほか)でも本人が詳しく書いています。
旧幕臣でありながら、維新後に明治政府の要職に就いた勝や榎本武揚らの行動を“変節”と批判する福沢に、正面を切って、「行いは己のもの。批判は他人のもの。ワシのあずかり知らないことだ」と反論を返すだなんて、さすがは江戸っ子。
批判に対してすかさず、「そんなもん知るか!」と一蹴できたのも、それほど自分の行動に自信と誇りを持っていた裏返しと言えるでしょう。
西郷隆盛「平日道を踏まざる人は、事に臨みて狼狽し、処分の出来ぬものなり」

お次は、大久保利通&木戸孝允と“維新三傑”に数えられる西郷隆盛(1828~1877)。
「常日頃から道義をわきまえていない、正しい生き方をしていない人は、不測の事態が起きると慌てふためき、どうしていいかわからなくなるものだ」とは、いかにもどっしり構えて動じないイメージのある西郷さんらしい言葉です。
盟友の大久保らとは、西南戦争を契機に袂を分かつことになってしまいましたが、廃藩置県や徴兵制の施行、身分制度の廃止、太陽暦の採用などなど……後世に残した功績の大きさから言っても、彼もまた近代日本の礎を築いたひとり。戦前から読み継がれてきたその遺訓集『南洲翁遺訓』(岩波文庫ほか)には、冒頭の言葉をはじめ、現代にも通じる含蓄のある教えが数多く収録されています。
渋沢栄一「ただ悪い事をせぬというのみにては。世にありて、何も効能もない」

令和のこのご時世に、4番を託すとなれば、そこは1万円札の現在の“顔”。激動の時代を駆け抜けた“資本主義の父”渋沢栄一(1840~1931)こそ適任でしょう。
なにやら意味深ですが、「悪いことをしない。ただそれだけでは、世の中に対して、なにを為したことにもならない」とは、なるほど、清濁併せ呑みながら時代を切り拓いていった渋沢らしい言い回し。『渋沢栄一訓言集』にもしっかり収録されています。
悪すぎた女グセのせいで、「ご祝儀にふさわしくない」なんて“謎マナー”も生まれてしまっている今日この頃ですが、コトを為そうと思えば、なりふり構っていられないことも時にはある。悪事自慢ほどみっともないことはないですが、品行方正も度が過ぎると、「つまらない男」と笑われてしまうのがオチですしね。
小林一三「新事業の準備が十分にととのったら即突進すべし。一、二、三ではいけない。二は迷いである、自信のなさである」
クリーンアップの一翼を担う5番には、先の渋沢とも並び称される西の天才実業家、小林一三(1873~1957)を起用しましょう。
阪急電車や宝塚歌劇団、映画最大手の東宝。さらには、いまや阪神タイガースまでをも傘下にもつ、言わずと知れた阪急阪神東宝グループの“生みの親”。
『天才実業家 小林一三・価千金の言葉』(小堺昭三著/ロングセラーズ刊)で紹介されている冒頭の言葉からも、“ゼロイチ”で立ち上げた鉄道事業を沿線の宅地開発とセットで一気呵成に推し進めた一三らしさがダダ漏れ。「二は迷いである!」なんて、まさに名は体を表しているとしか思えません。
ちなみに、いまや全国的に大人気のタカラヅカも、元は新興住宅地で他に何もなかった宝塚の街に人を呼び込むための集客施設として作られたもの。これまたすっかりお馴染みの住宅ローンも、一三が他に先駆けて取り入れたアイデアのひとつです。
松下幸之助「毎日が新しく、毎日が門出である」
さらに6番も、一三と同じく関西が輩出した稀代のカリスマ経営者の言葉。
現在のパナソニック、かつての松下電器産業を一代で築いた松下幸之助(1894~1989)は、その出版部門で名言や自己啓発ジャンルのベストセラーを数多く世に送りだす民間のシンクタンク『PHP研究所』の創設者としても、よく知られます。
ゆえに冒頭の言葉も、出典は、そのPHP研究所から刊行されている彼の自著『道をひらく』から。ちなみに、ここでの「PHP」とは、思想家としての顔もあった彼自身が提唱した幸福追求運動“Peace and Happiness through Prosperity”(=「繁栄によって平和と幸福を」の意”)に由来します。
そんな当該の自著のなかで、彼は「他人の道に心をうばわれ、思案にくれて立ちすくんでいても、道はすこしもひらけない。道をひらくためには、まず歩まねばならぬ。心を定め、懸命に歩まねばならぬ」とも。
いまや世界に冠たる大企業となったパナソニックですが、幸之助が22歳で起業した当初は、主力の電球ソケットがまったく売れず、一時は廃業も考えたほどだったとか。
脇目も振らず、ひたすら己の信じた道を行く。結局はそれが「新しい門出」へのいちばんの早道なのかもしれませんよね。
本田宗一郎「失敗のない人生なんておもしろくないですね。歴史がないようなもんです」
下位打線と言えど、7番も日本を代表するトップランナー。いまやジェットまで飛ばす“世界のホンダ”を一代で築きあげたカリスマです。
いまでこそ世界的な自動車メーカーとして知られるホンダですが、一介の自動車修理工だった本田宗一郎(1906~1991)が28歳で独立した当初は、「売れる」と目をつけて始めたピストンリングの開発がうまくいかず、あっという間に貯金もゼロに。
その後の3年間を、浜松高等工業学校(現・静岡大工学部)でのリスキリングの期間に当てるなどして、ようやく事業を軌道に乗せることに成功したと言われます。
選者の真山氏も、自身の新刊『逆境に打ち勝った社長100の言葉』(彩図社文庫)で、当該の言葉を紹介していますので、さらに興味が沸いたという方は、そちらもぜひ手に取って、名言をより深く味わってみてはいかがでしょう。
安藤百福「素人だから飛躍できる。既存の枠、常識からはみ出した発想ができるからだ」
続く8番は、試行錯誤のすえに世界初のインスタントラーメンを生みだした安藤百福(1910~2007)。いまや日本の“国民食”と言っても過言ではないチキンラーメン、カップヌードルでおなじみ、日清食品の創業者です。
お湯をかけるだけでラーメンが食べられる…なんていう、当時としては斬新すぎるキテレツな発想が百福にできたのも、彼自身が「素人だったから」。出典元の『安藤百福のゼロからの「成功法則」 人生に遅すぎるということはない』(鈴田孝史編著/かんき出版刊)では、齢48から一発逆転を果たした彼の軌跡が詳しく紹介されています。
当の百福も、90歳を過ぎてから宇宙食開発プロジェクトに乗り出すなど、老いてますます好奇心旺盛。2007年に96歳で亡くなるまで、新しいもの、まだこの世にないものを生みだすことに意欲を燃やし続けた人でした。
井深大「常識と非常識がぶつかったときに、イノベーションが生まれる」
ソニー創業者のひとり、井深大(1908~1997)も先の百福と同様、その著書『井深大語録』(小学館文庫)のなかで「常識にとらわれてはいけない」と説いています。
トランジスタラジオに始まり、トリニトロンテレビ、ベータマックスなどなど…数多の“発明”で名を馳せたソニーですが、井深の思想がもっとも色濃く反映されたアイテムのひとつが、かつて一世を風靡した“ウォークマン”。
音楽プレイヤーを持ち歩くなんて発想は、当時まさに“非常識”。それを持ちまえの技術力で軽やかに覆してみせるオリジナリティこそが、のちのPlayStationなどにも繋がっていくソニー製品の愛されるゆえんでもあったのです。
ちなみに、1973年にノーベル物理学賞を受賞した日本を代表する物理学者で、かつてソニーの前身・東京通信工業の社員でもあった江崎玲於奈は、井深の死に際して、その弔辞で「温故知新という言葉があるが、井深さんは違った。未来を考え、見ることで、現在を、明日を知る人だった」とも評しています。
田中角栄「どんな話でも、ポイントは結局一つだ。そこを見抜ければ、物事は三分あれば片付く」

さて、日本屈指の強力打線がこうして完成しても、先発投手がきっちり仕事をしてくれないことには、試合にはなりません。その意味でも、最後は死後30年以上が経っても、いまだ“待望論”が消えないこの人、田中角栄(1918~1993)に託しましょう。
首相在任当時には、政治家や官僚、大勢の陳情客たちが東京・目白の自宅に朝早くから押しかける“目白詣で”がおなじみの光景(そんな“目白御殿”が失火で全焼してしまったたのは、ちょうど1年前の年明けでした)。
その数は多いときで400人近くにも上ったようですが、さすが「決断と実行」をスローガンに掲げる角栄だけに、そこでも常に即断即決。どんな大物が相手でも決まって3分で話を切りあげ、テキパキと陳情をさばいていったとか。
このあたりの内幕については、出典元である『田中角栄 処世の奥義』(小林吉弥著/講談社刊)をぜひご参照を。この混迷の令和に、強力なリーダーシップをもつ“今太閤”が待望される理由もきっとよくわかるはずですよ。
鈴木 長月(すずきちょうげつ)/1979年、大阪府生まれ。関西学院大学卒。実話誌の編集を経て、ライターとして独立。現在は、スポーツや映画・アニメから、歴史・グルメまで、あらゆる分野で雑文を書き散らす日々。趣味はプロ野球観戦とお城巡り。本サイトでは「昭和プロ野球 伝説の「10・19」秘話 閑古鳥の鳴く川崎球場が日本でいちばん熱かった日」「男の日帰り“ちょい”城旅<神奈川県小田原 前編・後編>」「JR東日本の『どこかにビューーン!』で、ビューンと出かけてみた結果」「米・エミー総ナメ『SHOGUN 将軍』で話題! 年末年始に一気見したい真田広之のハリウッド出演作4選」「“松坂世代”上重聡さんインタビュー/前・後編」などを執筆。