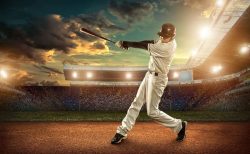高校野球では、延長戦に突入すると選手の負担が大きくなり、体力面や健康面への影響が懸念されます。その対策として導入されたのが「タイブレーク制」です。
現在では全国大会や地方大会でも採用されており、延長戦の新たな形として定着しています。試合を早く決着させるだけでなく、指導者や選手にとっては一瞬の判断が勝敗を左右する大きな駆け引きの場にもなっています。
タイブレークのルール
高校野球におけるタイブレークは、9回終了後の延長10回表から適用され、攻撃側は「無死一・二塁」の場面から打席に立ち、打順は前のイニングの続きとなります。
一塁走者には10回先頭打者の前の選手、二塁走者にはそのさらに前の打順の選手が入ります。15回までに決着がつかない場合はさらに続行されますが、投手の登板イニングには15回以内という制限があります。
選手の酷使を防ぎつつ、試合をスムーズに進める狙いが込められています。
導入の経緯
タイブレーク制が高校野球に初めて導入されたのは2018年春の選抜大会でした。当初は延長13回から適用されていましたが、選手の負担軽減や熱中症対策、大会スケジュールを円滑に進めるため、2022年度からは延長10回からに変更されました。夏の甲子園や地方大会でも採用され、現在では高校野球の大きな特徴の一つとなっています。
先攻と後攻、どちらが有利か?
これまで「後攻が有利」と言われることが多かったタイブレーク。しかし、近年は先攻の勝率が高まっています。2025年の地方大会決勝では11試合が延長タイブレークに突入し、そのうち7試合で先攻チームが勝利しました。
大阪大会決勝では、東大阪大柏原が延長10回表に勝ち越し打を放ち、大阪桐蔭を下した試合が象徴的でした。智弁和歌山の中谷仁監督は「先攻は気楽に攻められるが、後攻は失点すると精神的に追い込まれる」とコメントしています。
また、低反発バットの導入も影響しています。従来は長打で一気に試合を決める場面がありましたが、低反発化により長打が出にくくなり、タイブレークでは先攻が小技を絡めて得点を重ねるケースが増えました。
過去の甲子園の延長タイブレークでは、旧基準では後攻の勝率が高かった一方、新基準では先攻が勝ち越しており、環境の変化が結果に表れています。
タイブレークの戦い方
無死一・二塁から始まるタイブレークは、1イニングで勝負が決まる「短期決戦型」の場面です。最初に問われるのは、送りバントを選択するのか、それとも強打を狙うのか。打順の並びや投手の状態、控え選手の起用など、さまざまな要素を考慮して戦略を立てる必要があります。
特に重要なのは「バントの技術」です。普段は強打を任せる4番打者や主力打者に犠打を指示する場面もあり、選手に理解させておくことが欠かせません。
実際、国際大会のWBCでもアメリカ代表のスラッガーがバントを選択する場面がありました。負けたら終わりの短期決戦では「スモールベースボール」が有効で、バントができる強打者はそれだけで武器を増やすことになります。
高校野球のタイブレーク制は、選手の健康を守るために導入されましたが、同時に野球の奥深さを際立たせる仕組みでもあります。守りから試合を組み立てるのか、先攻で攻め切るのか。技術だけでなく、心理戦や準備力が勝敗を分けるタイブレークは、これからも高校野球の注目ポイントとなるでしょう!
タイブレークにおけるバントの重要性については以下の動画で紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。